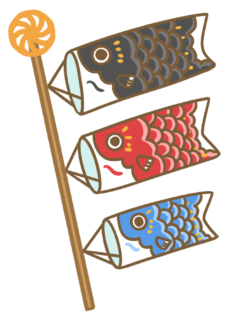
自宅から希学園に来るまでの間の道に、桜や銀杏の木を見かけます。少し前までは桜の木は淡い薄紅色の枝を広げ、銀杏の木はというと葉っぱが何もなくすこし寂しげに佇んでいたのですが、気がつけば桜も銀杏も青々とした葉が生い茂り、もうすっかり初夏になっています。世間ではもうすぐゴールデンウィークということもあり、受験生以外のご家庭では遊びに行ったり旅行に出かけたりする計画を立てていることでしょう。6年生にとっては新年度が始まってから3ヶ月。年度開始時に立てたスケジュールの修正をする時期です。まとまった休みを確保できるこの期間、せっかくですから有意義に使っていきたいですね。
タイトルに書いた「勝負の節句」は誤字というわけではなく、まさにこの「スケジュール調整をして闘うペースをしっかり構築する」勝負のタイミングという意味であえてこの字をあてました。イベントとして言うのであれば「菖蒲の節句」となりますね。説明するまでもありませんが、5月5日のことを指します。「端午の節句」として覚えている人は多いと思いますが、「菖蒲の節句」と聞いてすぐに思い浮かんできたでしょうか。
「節句」は年中行事を行う節目となる日を指し古くから大切に扱われてきましたが、これを江戸時代に幕府が公式に(今で言うところの)祝日として定めました。これが「五節句」の公式の始まりです。もちろん5日(回)あります。社会科の授業でも扱っていると思いますが、どの日のことで、何と呼ばれているか頭にぱっと浮かんできますか? 5月5日を「端午の節句」と呼ぶのは漢名(中国由来のイベントなので古い呼び名があります)ですが、日本での呼び方(和名)としては5月5日を「菖蒲の節句」と呼ぶように、それぞれの節句で植物の名前が使われているのでこちらも覚えておきたいところです。節句の名前や日付が怪しいな……という人のために書いておくと、1月7日が「人日の節句/七草の節句」、3月3日が「上巳の節句/桃の節句」、5月5日が「端午の節句/菖蒲の節句」、7月7日が「七夕の節句/笹の節句」、9月9日が「重陽の節句/菊の節句」となり、全部で5回。節句ごとに食べられる節句料理というものもあります。七草がゆや菱餅、柏餅あたりはすぐにイメージできると思いますが、七夕の節句で食される素麺や、重陽の節句で出される菊のお茶/お酒などは日頃こういったイベントに触れているか、あるいは勉強していないと頭に浮かんでこないかもしれません。
年中行事は一般常識として日頃何気なく参加したり通り過ぎたりしていることが多いと思いますが、まさに「常識」として入試問題に組み込むことが好きな学校もあります。その学校の特徴や校風、求める生徒の人物像がかいま見えますね。もしそういった学校を受験しようと考えているのであれば、面倒がらずに日常生活の中でのふとした疑問やイベント内容など、積極的に思考して学習に取り組んでいきたいものです。
ゴールデンウィークが終わると夏休みまで大型連休のない期間に入ります。大型連休がないということは勉強の進捗を調整するタイミングがとりづらいということになりますが、一週間が同じスケジュールで進むので勉強の予定がたてやすいとも言えます。この連休中に夏休みまでの過ごし方や勉強の進め方など計画をしっかり立てる、そしてその計画に基づきペースを守ってたゆまず地道に積み重ねていく、この下準備ができていると、天王山とも呼ばれる夏がより一層充実することでしょう。まとまった時間が取れる貴重な機会、有意義に使っていくことが重要です。スケジュールの立て方に悩んだり、困っている科目や単元が出てきたりしている場合は担当の講師やチューターにどんどん相談してください。ご相談、お待ちしています!

